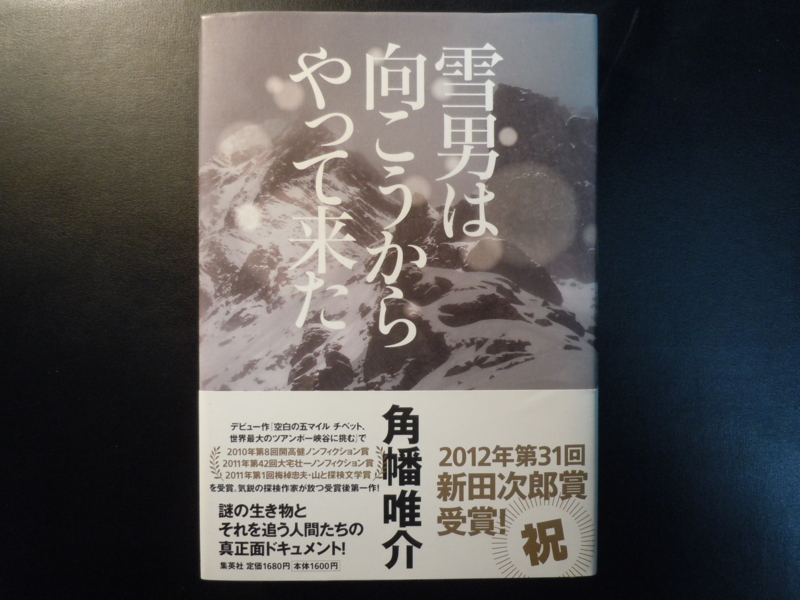一条真也です。
『テレキネシス』全4巻、東周斎雅楽作、芳崎せいむ画(小学館)を読みました。
「山手テレビキネマ室」というサブタイトルがついていますが、山手テレビというテレビ局で「金曜深夜テレビキネマ館」という番組を作る人々の物語で、古今東西のさまざまな映画の名作が紹介されています。
関東最大の民放局である山手テレビの裏側には、昭和30年代に建てられた旧社屋があります。その古いビルの地下には、「テレキネシス」と名づけられた小さな映写室があります。この作品は、そのテレキネシスの番人である山手テレビの超問題社員・東崋山と、正義感いっぱいの新入社員・野村真希乃が繰り広げる「映画」をめぐる物語です。
グータラ社員と真摯な若手女子社員のコンビは、同じ小学館の人気漫画である『美味しんぼ』を連想させますね。
ハリウッドの伝説的映画監督であるエリア・カザンにちなんだ名前を持つ華山は、かつてはヒット・ドラマを連発する名物プロデューサーでした。
しかし、ある不祥事をきっかけに深夜の映画番組担当という閑職に回されます。
ところが、崋山がセレクトして放映する「金曜深夜テレビキネマ館」は、観ると元気になれるという不思議な番組でカルト的な人気を誇っていました。
テレキネシスでは、基本的に古い名画が上演されます。CGを駆使した最近の映画に押されて埋もれつつある昔の映画を思い起こさせてくれます。そして、古き良き時代の精神を現代人たちに教えてくれる作品ばかりです。これまで古い映画を見なかった新入社員マキノも、徐々に映画の力に魅了されていくのでした。
最初に、紹介されるのが「風と共に去りぬ」です。主人公スカーレットがすべてを失うという大作ですが、これを会社にも妻にも見捨てられた同僚に見せるのです。
その同僚は、「何もかも失った人間が観るのに、これ以上の映画はなかったよ」とつぶやき、「ありがとう! スカーレットを観ていたら、とにかく根拠のない勇気が湧いてきた!」と他局に移って新しい人生を始めることを決心するのです。
小学3年生とのときにテレビの「水曜ロードショー」で観て以来、この「風と共に去りぬ」はわたしが一番好きな映画なので、最初に登場して嬉しかったです。
さて、謎が多い華山ですが、彼が山手テレビに入社したのには理由がありました。
彼の亡くなった父親は、映画監督でした。生前最後の作品のフィルムは行方不明とされていましたが、華山は山手テレビにフィルムが隠されていると推測するのです。
この漫画では、ずっと古い名作映画の紹介が続きますが、3巻の途中ぐらいから崋山の父親が遺した幻の映画フィルムをめぐって物語が大きく動きます。
3巻の後半から4巻のラストまでは息をもつかせぬ物語の展開があり、そこに名画の紹介もしっかり絡ませて、見事な構成でした。
この漫画の画を担当した芳崎せいむには、『金魚屋古書店』という作品があります。
漫画専門古書店の店員が、悩みを持った人に対して、その人にふさわしい漫画を紹介し、生きる活力を与えるという話の短編集です。
この『テレキネシス』はまさに『金魚屋古書店』の映画版で、仕事や人間関係で困難にぶつかった人が崋山おススメの映画をみて活路を見出すのです。
最初に登場する映画は「風と共に去りぬ」でしたが、最後に登場する映画は「オズの魔法使い」でした。亡くなった崋山の父親の遺作は、この名作ミュジージカル映画へのオマージュだったのです。この「オズの魔法使い」もわたしの大好きな映画です。
思えば、この映画を観てから、わたしはファンタジーの世界に魅せられたのでした。
主演のジュディ・ガーランドが歌う「虹の彼方へ」も素晴らしい名曲でした。
後に、あれは実際に彼女が歌ってはいなかったと知りましたが、そんなことは関係なく、「虹の彼方へ」は、今でもわたしにとって最高の「こころの歌」です。
それにしても「風と共に去りぬ」で始まり、「オズの魔法使い」で終わるというところが泣かせます。幼いわたしに「愛」と「夢」の素晴らしさを教えてくれたこの二大名画は、ともに1939年に公開されています。
そう、この二作は同じ年のアカデミー賞を競ったのでした。
さらに、1939年にはアメリカ映画最大の名匠ジョン・フォードの西部劇の最高傑作「駅馬車」までも公開されています。まさに「奇跡の1939年」ですが、日本との開戦直前にこのような凄い名画を同時に作ったアメリカの国力には呆然とするばかりです。わたしは、アメリカという国があまり好きではないのですが、ハリウッドから多くの名画を日本にプレゼントしてくれたことだけは感謝すべきであると思います。
最後に、この『テレキネシス』には「風と共に去りぬ」や「オズの魔法使い」といった超有名な作品ばかり紹介されているわけではありません。
あまり知られていない名作や、わたしが未見の作品も多数ありました。それぞれの作品には、詳細な解説コラムもついており、本書は映画ガイドとしても大いに使えます。
いま、わたしの目の前の4冊のコミック本には、大量のポストイットが貼られています。
これからDVDを注文して観賞したいと思っている映画たちのコラムのページです。
「エルマー・ガントリー」「大いなる勇者」「アスファルト・ジャングル」「ジュニア・ボナー 華麗なる挑戦」「ミスタア・ロバーツ」「砂漠の戦場 エル・アラメン」「パットン大戦車軍団」「シェナンドー河」「俺たちは天使じゃない」・・・・・これらの映画を観れば、だいたい本書に登場するすべての作品はカバーできると思います。
もちろん、わたしが未見の映画で、DVDも発売されていない作品もありますが。
それらの作品は、「縁」があれば、ぜひ観賞したいものです。それにしても、これから観るべき多くの映画が残されているなんて、なんて幸せなことでしょうか!
本書には、名画の紹介だけでなく、心に残る名セリフもありました。
第3巻の「シェナンドー河」のエピソードで、崋山がマキノに「何のために映画はあるのか」という本質論を語る場面があります。
そこで崋山は、「映画はな、現実に潜むドラマを見逃すな! 感動を見逃すな! そのための仮想現実として、感受性を磨く道具なんだって今は思ってる」と語ります。
そして、それ以上の意義が映画にはあるとして、「涙」という言葉をつぶやきます。
「涙?」と不思議そうに問い返すマキノに対して、崋山は言います。
「不幸じゃないのに、なぜか悲しい夢を見て、号泣して目が覚めたことってないか?」
「あるある、あります! なのに、どういう夢を見たか忘れていたり・・・・・そのくせ妙にさわやかな感じがしたり・・・・・」と言うマキノ。「大地に雨が必要なように、人には定期的に涙が必要なんじゃないかなあ」と言う崋山。
そして、「定期的に泣くこと?」と問うマキノに、崋山は「きっと映画は、実際の人生でなかなか泣けない人のために存在しているんだよ」と語るのでした。
わたしは、この崋山のセリフを読んで、なぜ自分が忙しい時間をやり繰りしてまで映画を観続けているのか、その理由がわかったような気がしました。
たしかに、暗い映画館で、さまざまな映画を観て、わたしは涙を流しています。
映画館の闇は、その涙を隠してくれるためにあるのかもしれません。そして、映画で他人の人生を仮想体験して涙を流した後は、心が洗われたようになるのです。
『涙は世界で一番小さな海』(三五館)に書いたように、わたしは人間にとっての涙の意味を考え続けてきましたので、崋山の「きっと映画は、実際の人生でなかなか泣けない人のために存在しているんだよ」というセリフはとても納得できました。
もう1つ、本書で心に残ったセリフがあります。
第4巻の「ジキル博士とハイド氏」というエピソードに出てきます。ドラマの売れっ子プロデューサーだった崋山が、ある俳優を重要な役で起用しようとします。
しかし、その俳優は小劇団で悪役を演じるだけの無名な人物で、しかも重病を抱えていて、余命いくばくもありませんでした。
その俳優の実力を見抜いていた崋山は、テレビに出演するように説得します。
体調を理由に断る俳優に崋山は、こう言うのでした。
「オレの仕事はドラマです。いいドラマを作って、テレビの向こう側の何万人もの視聴者を感動させることです。でも、もう1つ使命がある! ドキュメンタリーです」
「ドキュメンタリー?」と聞き返す俳優に対して、崋山は言います。
「すごい役者達を記録する。記録して視聴者の記憶に残す! オレはあんたのために出演をお願いしてるんじゃない! オレ自身のためです!」
この言葉に心を打たれた俳優は結局、崋山のテレビ・ドラマに出演を果たすのですが、わたしも感動しました。
ブログ「ヘルタースケルター」で、わたしは次のように書きました。
「この作品は、映画というよりも人類の『美』の記録映像としての価値があるとさえ思いました。沢尻エリカの人生には今後さまざまな試練が待っているとは思いますが、こんなに綺麗な姿をフィルムに残せたのですから、『これで良し』としなければなりませんね」
この言葉は、崋山のセリフから影響を受けたことを告白しておきます。
このようなセリフを崋山に吐かせた原作者の東周斎雅楽氏は、心の底から映画やドラマを愛しているのでしょう。
*このブログ記事は、1990本目です。
2012年8月28日 一条真也拝